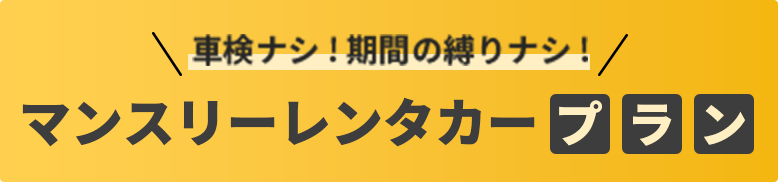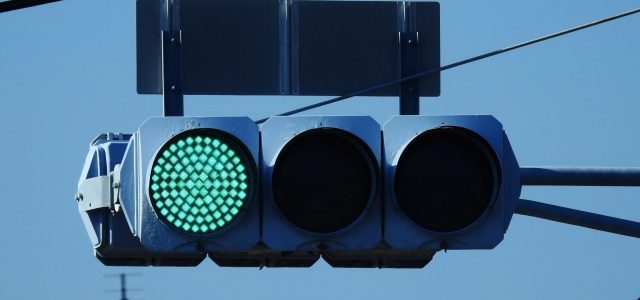こんにちは、賃貸自動車福岡店でございます。
4月も終盤になり福岡の久留米では29度 熊本県 鹿屋市では30度越えと春が終わりを告げております。
これからGW お盆と行楽の季節がやってまいりますが、新型コロナウィルスの影響で飛行機・電車での移動 繁華街・人が集まる観光地への旅行は行き辛い状況でございます。 そのような状況ですと、車で少し遠くの人が集まりにくい田舎の方へお出かけされるという方も多いかと思います。
都会では、あまり気にされている方はいませんが、田舎では気を付けたい運転時のルール前照灯についてお話させていただきます。
前照灯(ヘッドライト)はロービーム(下向き)・ハイビーム(上向き)があります。都心部で主に車を利用されている方は平時はロービーム 見通しの悪いときはハイビームと区別されている方が非常に多いですが、道路交通法では前照灯はハイビームを基本とし、対向車等とすれ違う際ロービームを使用するとなっております。
都会ですと常に対向車とすれ違っている状況な上、街灯もたくさんあり明るい為気になりませんが、少し田舎に行くとロービームでの運転は非常に危ない行為となります。
正しい前照灯の使い方をマスターし安全にドライブを楽しんでください。