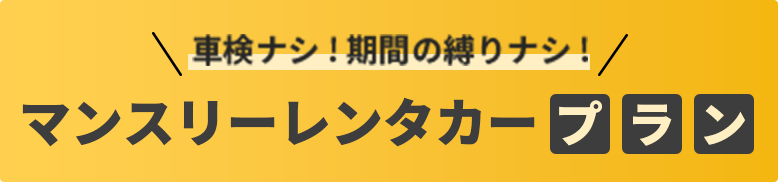こんにちは マンスリーレンタカー賃貸自動車 岡山店 でございます。
お車を運転中に信号機のない横断歩道にて、歩行者や自転車など横断待ちをされているのを見かけると思います。
みなさまはそのような場合どうされますか?
ある調査によりますと、信号機のない横断歩道での停止率は全国平均で21.3%となり、岡山県内の一時停止率は7.1%と9割以上が一時停止をしなかったという調査結果がありました。
運転者は常に歩行者または自転車が安全に横断歩道または自転車横断帯を渡れるように保護しなければなりません。道路交通法第38条第六節の二には横断歩行者等の保護のための通行方法に
⑴歩行者等の有無を確認できなければ、横断歩道等の停止位置で止まれるような速度で進行する
⑵横断しようとしている、あるいは横断中の歩行者等がいるときは必ず一時停止をする
⑶横断歩道等およびその手前30mは追い越しや追い抜きが禁止
などが規定されております。
横断歩道等を渡ろうとしている歩行者等がいる場合、運転者は横断歩道の直前で車を一時停止させ通行を妨げないように義務付けております。幼いお子さんや高齢者の方は横断歩道等を渡るのに時間がかかってしまいますが、もちろん例外ではございません。
信号機のない横断歩道等の手前には、横断歩道等ありの道路標識や路面標示が設置されています。この表示が見えたら歩行者等の有無をしっかりと確認をしましょう。
一時停止をする場合に後続車の追突事故を防止するために、早めにブレーキを踏み停止する意思を伝えましょう。また、歩行者等が渡ろうとしているのか立っているだけなのか判断に困る場合には、いつでも停止できるように速度を落として走行する事も大切です。
対向車線の渋滞や停止している車の陰など、歩行者等を見落としやすい場合も街中では多く存在しますが、私自身も歩行者や周りの車両に思いやりをもった運転を心掛けたいと思います。