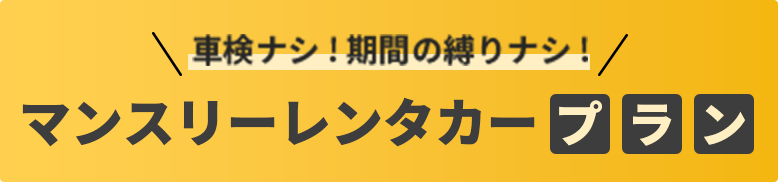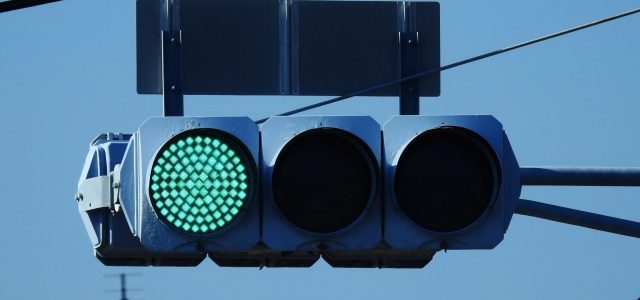こんにちは マンスリーレンタカー 賃貸自動車 岡山店でございます。
安全な道路交通に欠かせない信号機ですが、一般的な表示の色は赤・黄・緑の3色になっているかと思います。しかしながら法令上では青と定められているんです。
信号機の色は国際照明委員会によって赤・黄・緑・青・白の5色と定められています。青・白については航空信号機などに使われています。交通信号機には遠距離からでも人が認識しやすいと言われている赤・黄・緑の3色が使用されています。
1930年頃に日本で最初に信号機が設置された当時は、日本の法律上でも緑色信号と決められていて「緑信号」と呼ばれていたそうです。
信号機設置を報道した記事などが青信号と記載して報道したため、一般的に青信号と言う言葉が広がったと言われています。青信号と言う言葉が定着し1947年には法令上でも青信号と呼ぶように改正されていきました。
緑の芝生や春の新緑を青々としていると表現する日本独特の文化的特徴と光の三原色と同じ赤・青・緑と呼ぶ方がわかりやすいことからも青信号という言い方が定着していきました。
一般的な横型の信号機の配列は青・黄・赤に、縦型の信号機については上から赤・黄・青と順番が決められております。横型の信号機の場合には、最も重要な赤信号が樹木や看板などで隠れてしまうのを防ぐ為に道路の端から中央寄りに配置されています。ドライバーから見えやすい位置へ設置するのが目的となります。
スムーズな交通の流れや車輛の安全運航に欠かせない交通信号機ですが、時代と共に変化していきながら私たちの交通安全を守る機能として進化をしていくんですね。